本当は面白い作業服の豆知識 「作業服に使われる素材」について徹底解説

綿素材、ポリエステル素材、混紡素材。
作業服には、さまざまな素材が使われています。着用する環境によって適した素材は変わるため、それぞれの違いについて学んでおくことが肝心です。
本記事では、作業服に使われる素材の基礎知識から、ちょっとマニアックな知識まで解説していきます。
地味なようで、けっこう面白い「素材」の世界。知っておくと、作業服選びに役立つこと間違いなしです。
作業服に使われている素材とは? 天然素材・合成素材・混紡素材のメリット・デメリット
作業服に使われている素材は、大まかに分類すると3種類に分けられます。
- 天然繊維の素材
- 合成繊維の素材
- 混紡の素材
それぞれ、さらに細かく解説していきます。
天然繊維の素材
天然繊維とは、自然界に存在する素材を主原料に使った繊維のことです。植物繊維と動物繊維の2種類があります。
植物繊維の代表的な素材としては
- 綿(コットン)
- 麻(リネン)
などが挙げられます。なかでも、一般的な作業服にもっとも多く使われているのが綿です。

そして、動物繊維の代表的な素材には
- ウール(羊毛)
- シルク(絹)
- カシミヤ(山羊毛)
があります。保温性や保湿性にすぐれているため、防寒着などに採用されています。

天然素材のメリット
・肌触り・着心地の良さ
しなやかな感触で、サラリとした着心地が得られます。長時間の着用でも快適です。肌への負担が少ないため、敏感肌の方でも安心して着られます。
・丈夫さ
頑丈なため、作業着のようにハードな環境下で着用するウェアにはピッタリです。
・吸水性・吸湿性の高さ
よく水分を吸い、身体から排出された汗も素早く吸収してくれます。蒸れにくく、快適なコンディションを維持できます。
・熱に強い(植物繊維)
合成素材と比べて高温環境に強いため、溶接工場などでも十分に活用できます。
・保温性・保湿性が高い(動物繊維)
動物の毛を使用しているため、保温性や保湿性にすぐれています。そのため、アウターなどによく使われています。
天然素材のデメリット
・シワになりやすい
天然素材は、水分を吸収すると繊維が膨らみ、脱水時にそのまま固まるため、シワが発生しやすい構造です。毎日のアイロンがけが必要になる可能性があります。
・サイズが縮みやすい
洗濯と乾燥を繰り返すことで生地の組織が収縮していきます。洗濯の際にはネット等を使用したり、乾燥する際には平干しをしたりして、縮ませないように気を付ける必要があります。
・色落ち・色移りしやすい
天然素材は、化学素材に比べて染色堅牢度(染色の丈夫さの度合いであり、色落ちに対する耐久度のようなもの)が低いため、他の衣類と一緒に洗う際には洗濯ネットに入れた方がよいでしょう。

合成繊維の素材
石油などを主原料として、人工的に作られた繊維が合成繊維です。
代表的な素材としては
- ポリエステル
- ナイロン
- アクリル
- ポリウレタン
などが挙げられます。ポリエステルが作業服ではもっとも多く使われている合成繊維です。

合成素材のメリット
・摩耗に強く、耐久性にすぐれている
高い強度を持ち、とても頑丈です。破損・摩耗しづらいため、作業服には最適な素材といえるでしょう。
・軽い
軽量で動きやすいため、作業効率が高められます。
・シワになりづらい
形状記憶性が高くイージーケアであり、毎日の着用に適しています。
・安価で提供できる
天然素材と比べて低いコストで大量生産できるため、商品を安い価格で提供できます。
・デザインの自由度が高い
加工しやすいことからデザインの選択肢が多く、個性的な外観の商品が作りやすくなっています。

合成素材のデメリット
・肌への負担が強い
合成素材は静電気が発生しやすいため、敏感肌の方や赤ちゃんなど、肌が弱い方は、肌荒れ・炎症などを引き起こしてしまう可能性があります。
・吸水性・吸湿性が低い
汗を吸い取りづらいため、暑い日にはベタついてしまうことも考えられます。
・熱に弱い
高温環境では溶けてしまう可能性があるため、溶接工場などでの活用には向いていません。また乾燥機やアイロンにかける場合には設定温度を高く上げすぎないようにする必要があります。
混紡素材
複数の繊維を混ぜて紡績したものを、混紡素材といいます。繊維同士を混ぜることで、それぞれのデメリットを補った生地が作れます。
ゴールデンブレンドとは?
我々の業界では「ポリエステル65%・綿35%」で混紡した素材を「ゴールデンブレンド」と呼んでいます。綿の特性とポリエステルの特性をもっとも引き出せ、またデメリットも補い合えるベストの割合とされているからです。作業服だけではなく、一般衣料品の製造においてもよく使われている割合です。
作業服の生地に関する、ちょっとマニアックな用語をご紹介!
次に、作業服の生地に関してのマニアックな用語について説明していきます。
T/C・テトロン
T/Cとは、テトロン(Tetoron)とコットン(Cotton)を混紡した素材のことです。
テトロンとは帝人と東レが共同で生産するポリエステル糸の名称であり、2社の共同商標です。帝人の「テ」、東レの「ト」、雪いてナイロンの「ロン」が組み合わさった言葉となります。かつて東レと帝人がイギリスからポリエステル繊維の生産ライセンスを独占していた経緯があり、この2社の製造するポリエステルは今でもテトロンと呼ばれています。
そのため本来はその2社以外が製造するポリエステル糸に関してはテトロンとは呼べないはずのですが、現状、T/Cという言葉は「ポリエステルと綿の混紡素材」の総称のような意味合いとして広く使われてしまっているようです。
裏綿
表地がポリエステル100%で、裏地がポリエステルと綿の混紡素材を使っているものを指します。
交織
「こうしょく」と読みます。綿糸とポリエステル糸の混用など、異素材の糸を組み合わせることをいいます。
CVC
「Chief Value Cotton」の略語であり、綿の割合が50%以上を占める混紡素材を使った布地・製品などのことです。
平織り
縦糸と横糸を1本ずつ交互に浮き沈みさせて織る手法です。もっとも基本的な織り方といえます。
密度が高いため摩擦に強く、とても丈夫です。プリント加工のしやすさも魅力となります。デメリットは、厚手の織物が作りにくいところです。
綾織り・斜文織り(ツイル)
糸の交差部分が斜め方向に連続する(畝が斜めに作られる)よう織る手法です。英語ではツイルと呼びます。斜め方向にできる畝のことを「綾目」といいます。右上がりの綾目は「右綾」もしくは「正斜文」、左上がりの綾目のことを「左綾」、もしくは「逆斜文」と呼びます。
柔らかく光沢があり、シワが付きにくく、ストレッチ性にすぐれているという強みを持ちます。糸の交差点が平織りと比べて少ないため、頑丈さに欠けるのが難点です。
朱子織り・繻子織り(サテン)
縦糸と横糸の交差点をできるだけ作らないようにした織り方で、英語ではサテンと呼びます。
交差点が少ないため、表面が滑らかで光沢があり、高級な雰囲気が演出できます。しかしながら、摩擦や引っ張りに弱く、耐久性が高くはないため、作業着にはそれほど向いていません。またシワが付きやすいため、普段着にも適していません。
前述の平織り・綾織を含め、この3つの織り方を「三原組織」といいます。

素材別 おすすめ空調服・空調風神服
ここまで各素材について解説しましたが、ここからはそれぞれの素材のおススメの空調服・空調風神服についてご紹介します。
綿
自重堂 54110

ポプリン生地で表面の畝と光沢がが素材の品の良さを感じさせてくれます。
強度も強くアウトドアやハードワークにもご使用頂けます。肌触りの良さと着心地の良さが特徴です。
サンエス KF91490

デザインはスタンダードな作業服タイプでどのような方が着用してもフィットするデザインとなっており、企業様のユニフォームとしてもおすすめのモデルとなっています。また、素材には綿100%のコットンブロードを使用しているので、ハードワークな現場や火を扱う現場にも人気の商品です。
ポリエステル
コーコス G1919

見るものを引きつけるエッジの効いたデザインがカッコイイ『GLADIATOR』ブランドのカジュアル空調風神服G1919。
素材にはタスランリップストップ織ポリエステル100%を使用しており、生地の軽さ・優れた防シワ性・高い耐久性が特徴です。機能性にも拘りがあり、特に首回りの仕様を大きく取ったビッグネックフーディーは首・顔周りへの風量を大幅にアップしています。
ジーベック XE98020

空調服に最適と考えられる適度なハリ感がある東レ素材エアコンテック®にさらに抗菌防臭、防汚機能を付与したエアコンテック®テクノクリーンDEを使用した商品です。
猛暑と長時間の作業が重なると多量に汗をかく季節ですので身体のニオイが気になりますが、汗臭の元となるマイクロコッカス菌や生乾き臭の元となるモラクセラ菌の増殖を抑制します。生地自体が防臭効果を発揮する商品です。
混紡
アイトス AZ30587

高所作業に着用が義務付けられているフルハーネスが必要なケースでおすすめできるベスト型の空調服。シックなカラー展開の中でも配色をいれることがアクセントになっています。
高所での作業中にファンが落下し、思いがけない事故が起こらないようメッシュカバーを施しています。近年の異常な暑さにも対応できるよう、両脇下にはアイスパックポケットが付いており、保冷剤をいれることで、より涼しさを体感できます。
素材の知識を深く学ぶことで、自分に合った作業服が選べるようになる
作業服に使われる素材の基礎知識について解説し、少しマニアックな知識をご紹介いたしました。
素材に関する知識が高まることで、自分に合った作業服・ワークアイテムが選びやすくなります。
作業服をご購入いただく際の参考にしていただければ幸いです。


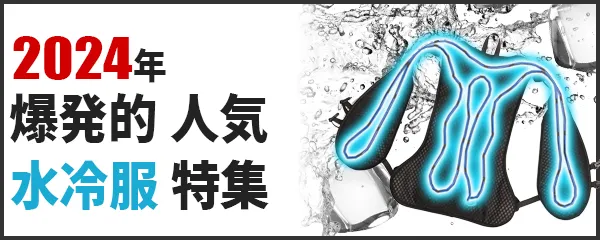





 作業着・ユニフォームのご相談
作業着・ユニフォームのご相談 空調服・空調風神服 専門店 ユニフォーム ステーション
空調服・空調風神服 専門店 ユニフォーム ステーション






















