コロナ禍での2021年 企業が生き残るために求められる力とは?

世界中で猛威をふるう新型コロナウイルス「COVID-19」は、私たちの日常生活だけではなく、産業のあり方や企業業績、雇用状況などにも甚大な影響を与えています。
今回は、コロナ禍で突入した2021年の企業経営において、生き残るためにはどのような力が必要なのか、解説します。
コロナウイルスがビジネスシーンに与えたもの

新型コロナウイルスの登場は、あらゆる産業に影響を与え、私たちの働く現場にも大きな変化をもたらしています。
とくに旅行業界や外食産業、エンターテインメント産業の被害は大きく、今まで経験したことのないような未曾有の状況という声も散見されます。
産業界が受けた大きな変化とは、大きく以下の2点に集約されます。
事業計画の修正や変更
まずは、事業計画の見直しや変更です。
社会の状況が一変してしまったため、当初の事業計画を大きく変更せざるを得ないような企業は多かったのではないでしょうか。
そして急激な業績悪化にともない、資金繰りが難しく倒産してしまう企業・お店も増加中です。
東京商工リサーチによる調査によると、2020年の飲食店廃業数は842件となり、これは過去最多の数字だそうです。
ワークスタイルの変化
次に、従業員のワークスタイルの変化です。
感染防止対策として3密の回避が叫ばれ、ソーシャルディスタンス(フィジカルディスタンス)を確保するためにテレワークなどの在宅勤務を導入する企業が増加しました。
また、時差通勤や業務におけるペーパーレス化の推進など、さまざまな施策が奨励されました。
この変化の波は強く、社会のあらゆる分野で影響を与えています。
そしてこれらの変化は、コロナウイルス後にも、ある程度定着する可能性があるだろうと言われています。
企業に求められる感染防止対策と、事業継続対応とは?

このようなパンデミック下においては、企業にもあらゆる対応が求められます。
具体的には、以下のような施策を取ることが重要です。
感染症対策の徹底
企業の経営者は、従業員への感染を予防するため、会社外に感染を広げないために、さまざまな対策を実施することが求められます。
まず、手洗いうがい、定期的な換気を徹底させます。皆が手をつける可能性のあるドア・ドアノブや、階段の手すり、エレベーターのスイッチ、その他共用している備品については、定期的な消毒をおこないます。
そして対面会議の削減や不要な外出、不調の従業員の早期把握、休暇や復帰の基準などを定めて周知させます。
業務の進行に関しては、可能な限りテレワークや時差出勤、社内でのソーシャルディスタンス(フィジカルディスタンス)を実現させ、3密の状況を作り出さないようにしましょう。
情報の収集・発信
感染症に対する情報を日々収集し、従業員に共有させます。また取引先や協力企業へ、自社でおこなっている感染対策の取り組みを発信しましょう。
事業継続対応
自然災害やパンデミックなど想定外の事態が発生した場合、事業資産の損害を最小限に留めて中核事業をどのように継続していくかの方法や手続きを記したものをBCP(Business Continuity Plan)といいます。日本語では「事業継続計画」となります。
日本においては、2011年の東日本大震災をきっかけとして、重要視されるようになりました。
緊急の事態が発生した場合、倒産や大きな事業縮小を避けるため、平時にBCPを念入りに策定しておくことが重要になります。
自然災害はおもに施設や設備が被害に遭うことが多く、パンデミックの場合はおもに人的資源が被害に遭うため、自然災害時とパンデミック時のBCPの内容は異なる場合があります。
コロナウイルスなどの感染症への対策には、経済産業省が2009年に発表した「新型インフルエンザ対策のための中小企業BCP策定指針」を参考に、BCPを策定するとよいでしょう。

一般的なBCPの策定手順
(1)BCP基本方針の立案
何のためにBCPを策定するのか、運用することにどのような意味があるのかを考えて、基本方針を立てていきます。
(2)策定・運用体制を確立する
BCPの策定・運用体制を決めます。
企業の状況を踏まえて、策定・運用する人材を決定し、取引先の企業などにも意見を聞きましょう。
また、BCPの策定・運用について従業員に周知させることも重要です。
(3)事業を理解する
どの事業が自社の中核事業であるかを考え、優先して継続させるべき事業をリストアップします。中核事業とは「売り上げに最も貢献する事業」や「自社のブランドや信頼を築くための事業」「納期などが遅延すると影響が大きい事業」などです。
そして、有事の場合には、その中核事業がどの程度の質を保ちながら継続できるかも考えておきます。
また、中核事業での重要業務を把握しておき、その業務を継続していくために必要な経営資源(従業員・設備・資金・情報など)を把握しておきましょう。
(4) 中核事業が受ける被害を想定する
次に、会社が受けうるリスクを具体的に想定します。
自然災害と違いパンデミックの場合には、設備や建物などの物的資源が被害を受ける可能性はほとんどありませんが、業務にかかわる人員の確保が難しくなる可能性があります。
ありとあらゆるリスクを想定し、書き出していきましょう。そして、想定されるリスクにある程度の順位付けをおこない、優先して対処するべきリスクを決定しておきます。
(5)BCPの実行条件を明確に決めておく
制作したBCPを実行する条件を具体的に決めておきましょう。
たとえば『国が「緊急事態宣言」を発動したら実行する』などです。
実行するにあたっての体制や、指揮系統なども、あらかじめ決めておく必要があります。
(6)BCPを定期的にチェックし、更新していく
有事の際、いざBCPを実行しようとしても、計画に記載された情報が古くては高い効果を得ることはできません。
定期的にBCPを見直し、会社の最新状況に合った計画にアップデートさせていくことが重要になります。
企業淘汰の時代 荒波を乗り越えられる強い企業経営

今回は、企業がコロナ禍の2021年をどう生き残っていくのか、必要な対応力について解説しました。
自然災害やパンデミックはいきなり訪れることも多いため、企業は事前にさまざまな対策を練っておく必要があります。
まだまだ厳しい環境が続く可能性が高い2021年、この荒波を上手に乗り切っていきましょう。


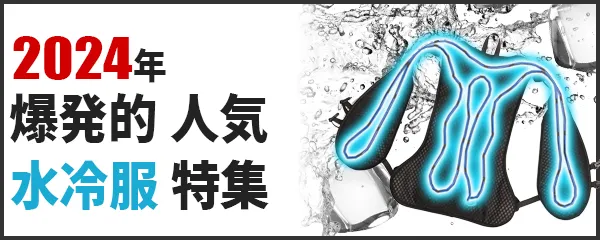

 作業着・ユニフォームのご相談
作業着・ユニフォームのご相談 空調服・空調風神服 専門店 ユニフォーム ステーション
空調服・空調風神服 専門店 ユニフォーム ステーション






















